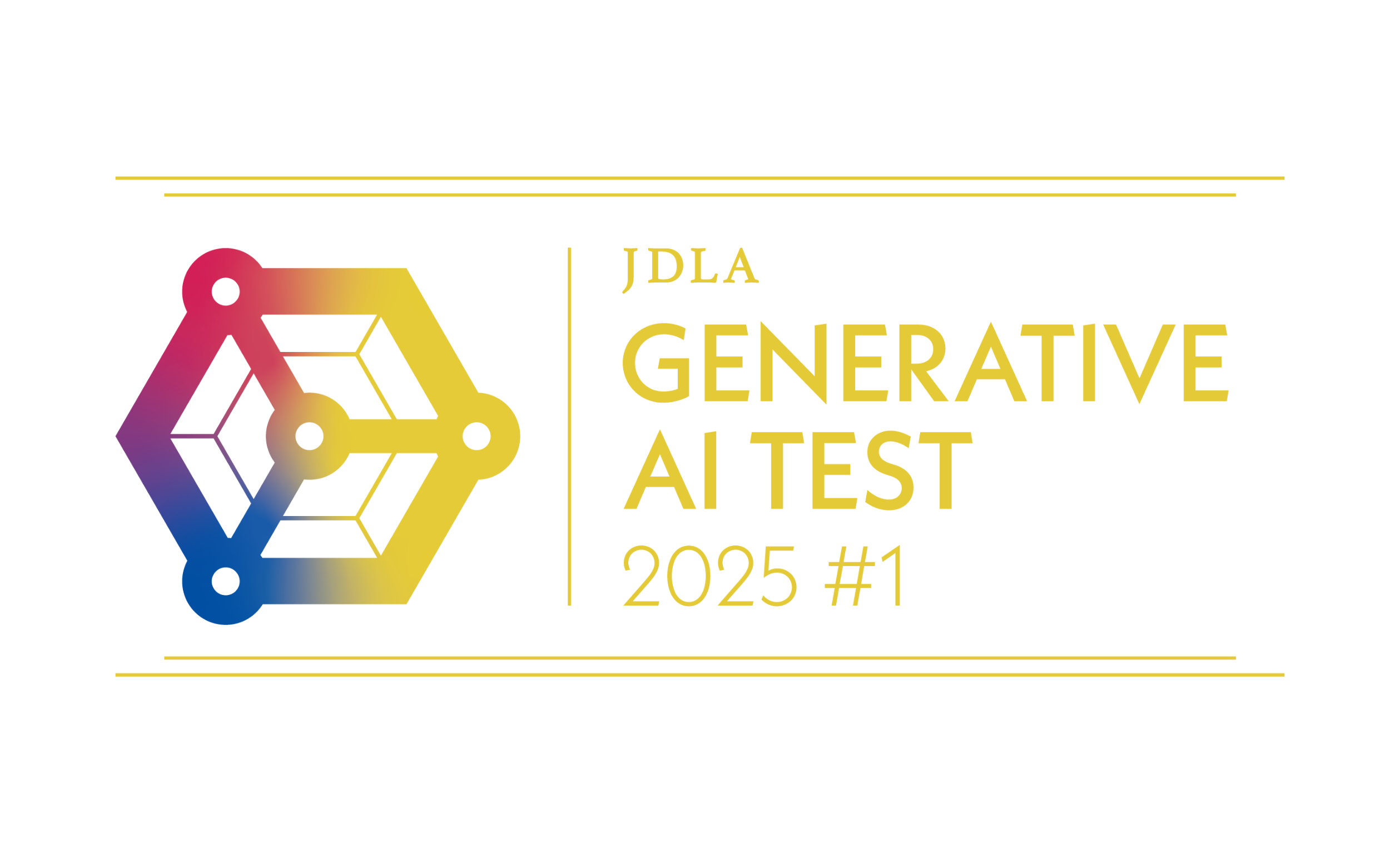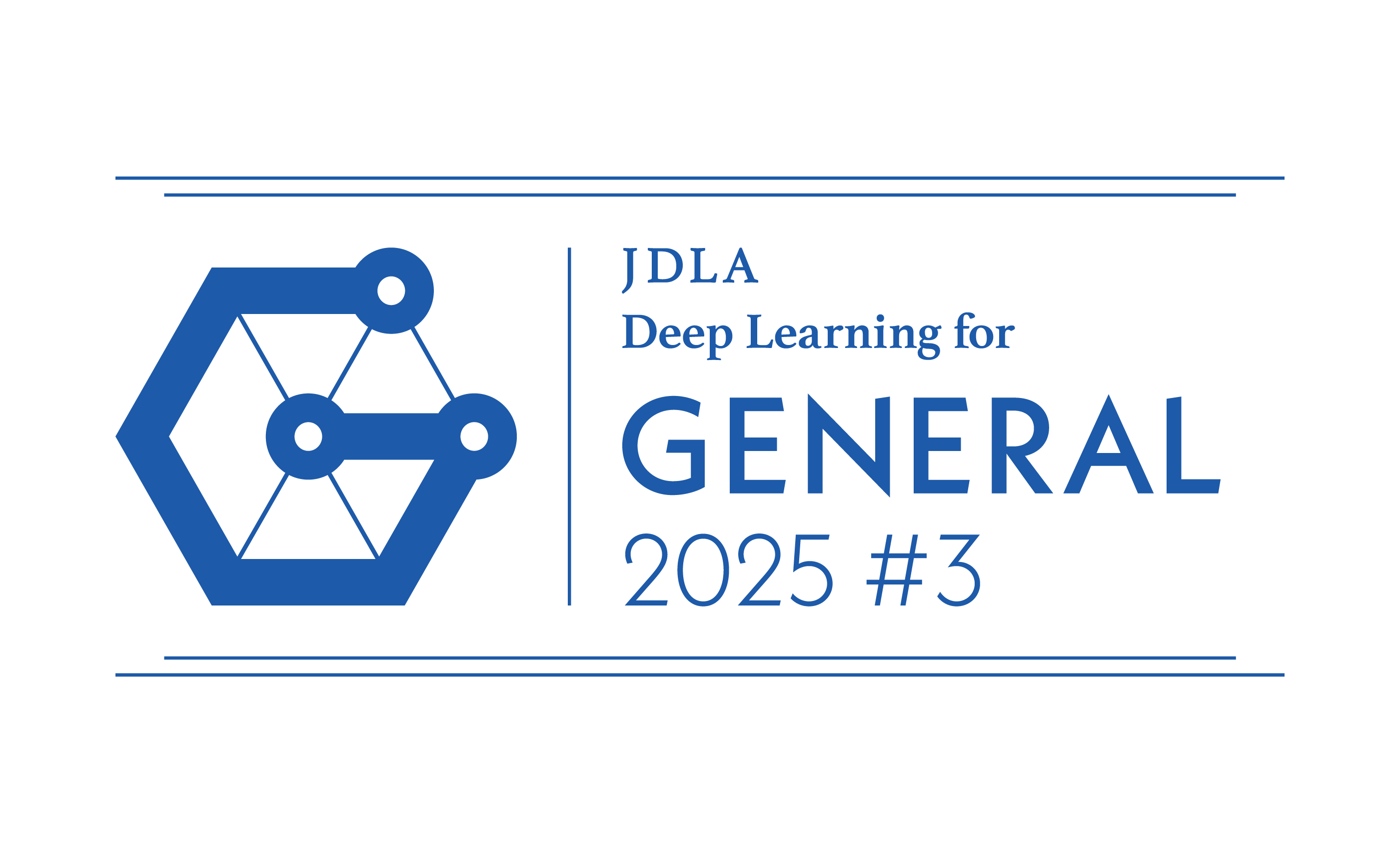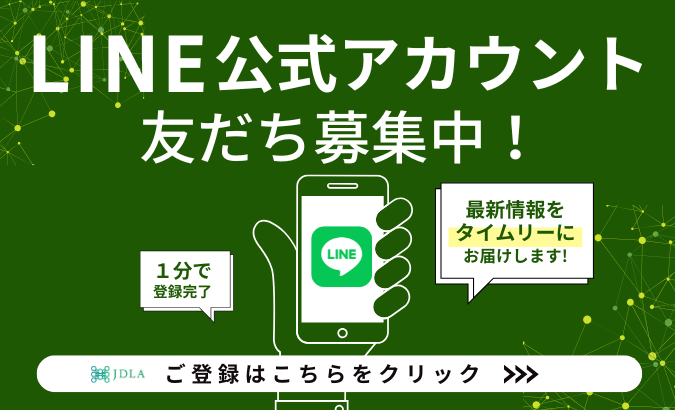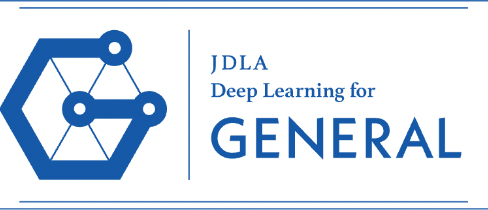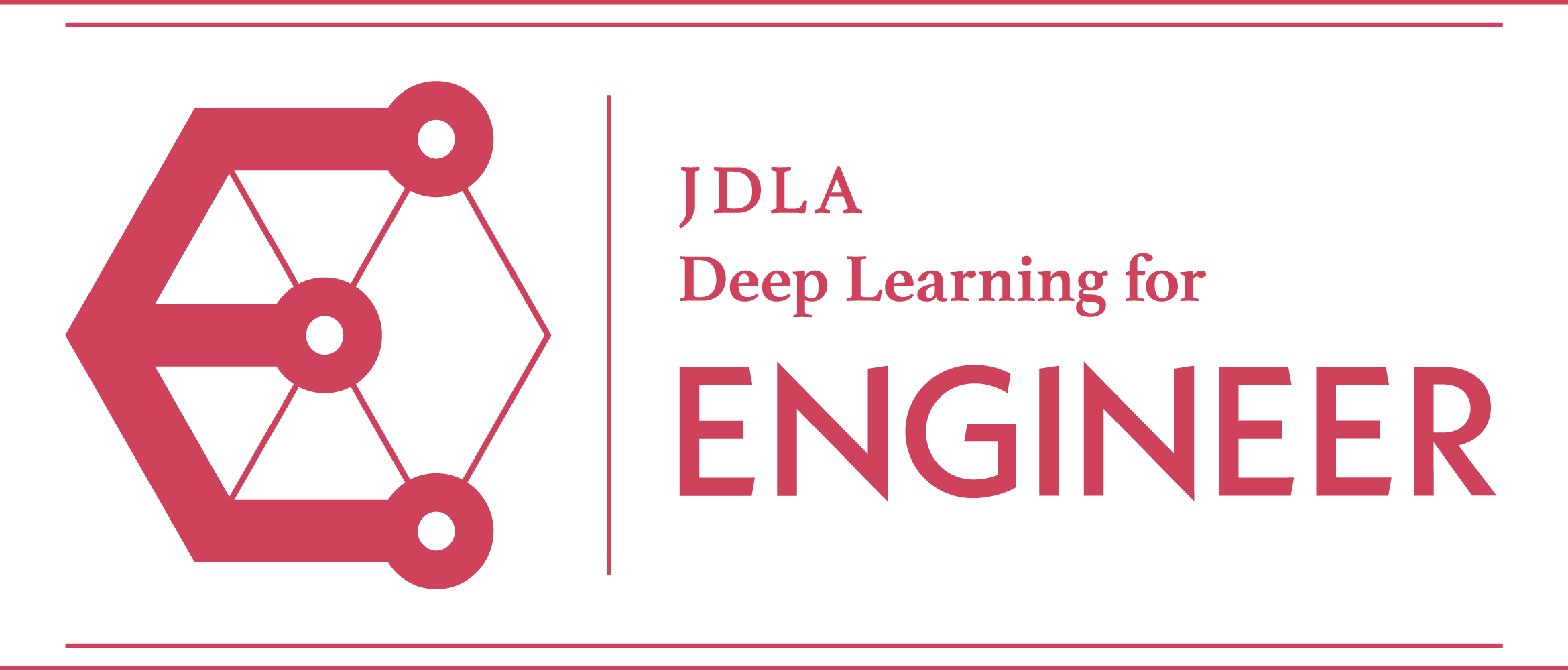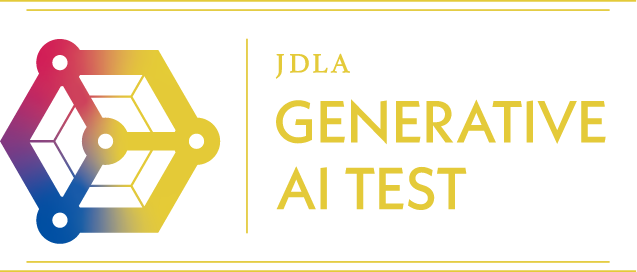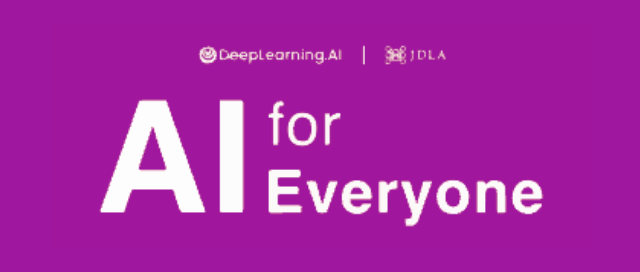中部大学 教授 藤吉 弘亘氏(左)Sky株式会社 河野 武氏(中)同 南野 浩一氏(右)
Sky株式会社(以下、Sky)は、藤原竜也さんのCMで有名な「SKYSEA Client View(スカイシー クライアント ビュー)」や吉田鋼太郎さんのCMで知られる「SKYPCE(スカイピース)」などのパッケージ商品開発を行うICTソリューション事業と、お客様の要望に応じて受託開発を行うクライアント・システム開発事業を大きな柱としています。
CMの影響もあり、パッケージ商品の印象が強いのですが、同社には創業以来、受託開発事業を中心的に行ってきた歴史があり、現在も売上の割合が大きいのはクライアント・システム開発(受託開発)事業の方です。電機メーカーや自動車業界のOEMメーカーやTier 1、金融業界、ネット業界などとくに分野を絞らず、幅広くソフトウェア開発をしています。また近年では、自動車、医療や建機、農機などいろいろな分野で増加するAI案件への取り組みを求められます。
そのような状況の中、Skyでは中でもAI人材育成への取り組みを積極的に進めています。特筆すべきは、同社技術アドバイザーである中部大学 藤吉弘亘氏(JDLA理事)のサポートを受け、「E資格プログラム認定事業者」となったことです。これにより、Skyは社内研修でE資格認定プログラムを実施できる国内唯一の企業となりました(2025年1月現在)。
今回、AI人材育成の取り組みを中心的に進めるクライアント・システム開発事業部のお二人と、取り組みをサポートしてきた藤吉教授にお話を伺いました。
Profile

Sky株式会社 クライアント・システム開発事業部 戦略技術部 次長
河野 武氏

Sky株式会社 クライアント・システム開発事業部 技術部 技術サブチーフ
南野 浩一氏

中部大学 工学部 教授
日本ディープラーニング協会 理事
藤吉 弘亘氏
AI人材研修が事業の成果に直結

――AI人材育成に注力するようになった背景を教えていただけますか?
河野 : 私は、弊社の中心的な事業である受託開発の事業部に所属しています。AI開発に取り組むお客様へ人材を提供し、開発の一部を請け負っています。また、私どもが主導してAI開発を推進する機会も増えています。会社全体ではパートナー様含めて5600名ほどの技術者がおり、その中に約150名のAIチームがおりますが、ここを増やしていき、事業を大きく伸ばしていきたいと考えています。
――藤吉先生が貴社の技術アドバイザーになったきっかけをお聞かせいただけますか??
河野 : 2018年にG検定合格者の交流を目的とした「合格者の会」で藤吉先生にご挨拶させていただいたことが最初のきっかけです。その後、先生のオープン研修に参加し、その場で弊社内の画像認識の研修をご相談し、快諾をいただきました。それ以降、毎年研修を実施していただき、そのうち技術的な相談などもお願いするようになり、弊社の技術アドバイザーになっていただいたという経緯があります。
藤吉 : Skyは人材教育を非常にしっかりやっている会社ですので、ちょっとした講座をやるだけではなく、E資格に必要な内容をカバーできるような研修を行ってきました
河野 : 実際に受講者もかなり多く、先生の画像認識やディープラーニングの研修は、年間100名ぐらいの受講者を集めています。

――まず、AI人材育成についての取り組みをお聞かせいただけますか?
河野 : AI人材はポッと出てくるものではありません。しかし素養のあるメンバーが新卒やキャリア採用で入って来ます。彼らをきっちり育成していくが必要があります。そのために育成の仕組みを作ってきました。
まず画像認識の教育用カリキュラム、そして機械学習用、ディープラーニング用のカリキュラムを作りました。技術を高めるための研修については、会社としても積極的に受けるように推進しており、研修に参加すること、カリキュラムを作る・実施することなどは会社の業務時間として認められますので、サービス残業のような形にはなりません。外部の研修を受けても、会社が費用を負担し出勤日として扱います。
本気でAI人材を増やすために研修の内製化を起案

――外部研修の費用を補助する会社は多いですが、カリキュラムや教材まで内製化するのは、かなりユニークだと思います。その理由と、内製化するメリットを教えていただけますか?
河野 : 最初にカリキュラムを作ったころには、外部にあまり望んだ研修がなかった時期でした。それなら自分たちで作った方が良いだろうと、まずは画像認識やディープラーニングのカリキュラムを作りました。内部研修に関しては藤吉先生からご紹介を受けた大学の先生方にもお願いしました。つい先日も、自然言語処理の岡崎直観先生(東京科学大学 情報理工学院 教授・JDLA理事)の内部研修を実施したところです。
外部研修は、もちろんそれはそれで必要ですが、あまり量は稼げません。2名や3名程度の参加になってしまいます。でも内部で研修を行えば、30名から40名が一挙に受けられます。研修の量をこなし、本気で技術者を増やしていこうとするなら、内製化の方が会社の方向性に合うと考えます。
藤吉 : ディープラーニングと言えば名刺を認識していくSKYPCE。河野さんの事業部ではありませんが、あれはディープラーニングをバリバリ使っています。
河野 : どのタイミングで話をしようかと思っていたのですが(笑)、パッケージ部門にはAIの技術の担当者がおりませんでした。私どもは本来受託開発担当なのですが、SKYPCEのAI対応はこちらでやっています。研修で学んだことが早速事業に活きた事例といえるでしょう。
――研修が事業の成果に直結するのはすばらしいですね。
藤吉 : 結構短い開発期間だったと思うのですが、実際に成果につながったのは良かったですね。当時、他社はディープラーニングベースではなかったんですよ。Skyではディープラーニングをどんどん適用し、精度が上がったわけです。
河野 : 一昨年の4月ぐらいから取り組んで、半年後には運用まで持っていきました。ディープラーニングによって精度は、もう格段に上がりましたね。
認定プログラム事業者になることでE資格を受験しやすくする

――E資格認定プログラム事業者になった背景を教えていただけないでしょうか?
河野 : そもそもAIの推奨資格としてJDLAのE資格を考えていました。藤吉先生のディープラーニング研修のおかげで、E資格取得に必要な内容をかなり習得できたのではないかと感じていました。もともと先生がいらっしゃる中部大学でE資格認定プログラムを提供されていて、これをSkyの社内研修で使ってはどうかと提案いただいたのです。そもそも内部で研修できる仕組みがあったわけではなかったのですが、前向きに考えようと段取りを踏み、見通しがついたところでスタートしました。
もっと私自身の想いをお話ししますと、もともと私はG検定を持っており、E資格も取るつもりだったのです。私は大阪の人間なのですが、その当時、東京のE資格認定プログラムを受講しに行こうとするとかなり時間と費用がかかるので、東京でE資格認定プログラムを受けるのは現実的ではないと感じました。いったん諦めたのですけれど、同じように考えている人が社内に多いことがわかりました。みんなE資格認定プログラムを受けて資格を取りたいと思っているのですが、E資格認定プログラムを受けるためのハードルが高くてなかなか受けられない。そうであれば、E資格認定プログラムの仕組みを提供すれば受けたい人はいっぱいいるはずです。E資格認定プログラムを提供することによってE資格の保有者を増やしていけば、育成強化につながります。それでE資格認定プログラム事業者になることを前向きに進めようと思ったのです。
――しかし会社を巻き込むのは大変ではありませんでしたか?
河野 : メンバーとくに若手のみなさんは受講費を会社に出して欲しいとは言い出せないでしょう。しかし社内研修であれば、みんな受けられるようになるのではと考え、社長にプレゼンしましたら、二つ返事でOKをいただきました。しかし、その後が問題でした。私どもに研修を行う仕組みがあるわけではありません。自分たちで構築していくのは大変でした。例えば演習をどういう形でやるのか。マシンを潤沢に用意できるわけではないので、実行環境をどうするか苦労しました。また、会社の研修担当部署との調整も必要でしたが、基本的に私どもが推進するということに落ち着きました。ここにいる南野が担当の一人になります。
――研修資料の作成も大変だったのでは?
河野 : ちょうどシラバスが切り替わるタイミングでしたので、南野を始めとするメンバーと従来のシラバスと新シラバスとを比較精査し、それぞれに資料や演習の作成を割り振りました。もちろん教材を作ることに慣れているわけではありません。どうしても悩むところが出てきて、そこは藤吉先生に相談しました。
南野 : 新しい追加部分の資料を、出来上がっている藤吉先生ベースの資料に、どうやってうまく組み込んだらいいか。また、きれいに全体をまとめるかというところは難しいと感じました。そもそもE資格を持っているメンバーが少ない中で、受講者が正しく学べる資料を作らなければなりません。結構、自分自身の勉強が必要でした。自分が担当する部分の用語に関してはしっかり勉強し、間違いがないように藤吉先生にもレビューしていただきながら進めておりました。
河野 : やはり藤吉先生の存在は大きかったですね。私どもはどうしても理論的に弱いところがあったりするので。
藤吉 : いやいや、私が渡した旧シラバスからの変更点はかなり量があったはずです。そこはしっかりやっていただけて、すばらしいと思います。
河野 : 私もE資格を取得できたのですが、これだけ教材作成をしたら、自分自身も勉強になって成長できたかなと思ったのですが、E資格の直前時期になり、改めて問題集を紐解こうとすると、結構わからない(笑)。認定プログラムはもちろん受けるとしても、しっかり問題集もやりこまなければならないのですね。今回受けてみたのですが、途中で「落ちたな」と思ってしまいました。結果的に受かったのですが、難しい資格なのだなと再認識しました。
認定事業者になったことが人材採用にもいい影響を
――社員のみなさんに受けてもらうために何か工夫されたこととはありますか?

南野 : 各自で行う演習については、自身のペースで進められるようにしました。実行環境に関しても、こちらでちゃんと準備しておいたので、そういうところも迷いなく進められるよう、できるだけサポートしたつもりです。
河野 : 研修担当部署と役割分担するようにしました。研修担当部署に出席や参加者の取りまとめをやってもらい、それ以外の情報展開や環境要因の説明は私どもの方でやりました。プログラムを作った後はなるべく研修担当部署の方におまかせするようにしました。
――こういう社員に受けてもらいたいということはありましたか?
河野 : まずAIの業務をやっているメンバーには、基本的にみんな受けてもらいたいという想いがあります。またキャリア採用や新卒で入ってこられる方には、極力みんな受けていただくようにと考えています。とくに職種やレベルを限定してはいませんが、会社の研修として受けていただく以上、資格に合格するまでは責任を持ってやってくださいというスタンスです。受けて終わりではなくて、合格するまでやっていただきます。
――実際の学習期間はどれくらいになるのでしょうか?
河野 : 8月のE資格の試験をターゲットとしますので、3月頃からスタートして7月頭ぐらいまでを期間としています、藤吉先生にもその間三回ぐらい研修を行っていただいています。学習時間は40時間から50時間ぐらいにはなりますね。
――前回の合格率はいかがでしたか? また合格した方からはどのような声があがってますか?
河野 : 65%が合格しました。全国平均と同じくらいで、まずまずかなと思っています。
南野 : 生成AIの業務に携わっている人から、プロンプトを書くときに構造を理解しながら命令を与えられるようになったとか、新たな業務での新しい対応方法を思いつくようになったとか、深い知識を得て業務で活かせるようになったという声がありました。
あと別の観点になりますが、新卒採用の時に応募者が、“JDLAのE資格認定事業者を調べていたらSkyがあって、そういう活動をしているんだと興味を持った”と言ってくれて、入社した方がいます。採用の面にもいい影響があったのではないでしょうか。
――それはうれしい効果でしたね。
南野 : そうですね。認定プログラムを通してはじめてE資格を知ったという人もいまして。“G検定は知っていたけどE資格は知らなかった”という人が受けるきっかけになったとか、他のAIチームがどういうことをやっているかという議論の内容が頭に入ってきやすくなったとか、AIに関するコミュニケーションがもっとしやすくなったという声も上がっています。
河野 : 1回目にしては、割りと期待した結果が出たかなと感じています。まずは受かるまでしっかりやって、しっかり結果を出してくれたというところは会社からも評価していただけたと思います。
――社長プレゼンでは、KPI的なものは約束されたのでしょうか?
河野 : KPI的なことは社長には話していません。E資格を取得することの意味合いと有用性とそれにかかる費用。例えば外部研修として、そういう研修を受けた場合どれぐらい費用がかかる。それを社内で実施することで、これぐらい抑えられるという費用対効果を説明しました。あと、先ほど南野が話したように、キャリア採用、新卒採用へのアピール効果が大きいことも訴求しました。
AIの知見を広げたメンバーの「質」が変わりつつある
――E資格取得者が増えていったら、こういう事業展開を行いたいなどのビジョンはありますか?

河野 : 基本的には、AIの技術者をより多く育成して、AIに関する受託開発をより多く受注し、身につけたAIに関する知見を活かしながら、業務を推進していくところにあります。
藤吉 : 第三者からの意見ですが、これまでは受託開発というと、テーマがあらかじめ決められて来るような案件が多かったと思います。しかし最近は、お客様に逆に提案できるような人材が育っている手応えを感じます。
河野 : そうですね。お客様から指示を受けてお手伝いするようなことが多かったのですけど、私どもが主導的にやっていける業務が増えてきたり、お客様がやりたいと言っていることに対して“こういう風にやればできるんじゃないでしょうか”と提案できる人材が増えています。
藤吉 : AI開発はただ設計書通りに作るという業務じゃないんですよね。そういったことに対応できる人材が求められ、それが育ってきているのかもしれませんね。
南野 : 私もそもそも入社した時点では、プログラミングもはじめてという新卒だったのですが、業務でAIを触っているうちに面白いなと思って、今回もE資格の運営に携わらせてもらいました。今後もAIに興味を持って入って来る新卒が多くいるはずです。そんな人たちがE資格を取得すれば、お客様に対してうちの強みになると思っています。
河野 :まずはE資格取得者50名を目指し、その先は300名まで増やしたいと考えています。
――これからの展開についてひと言お聞かせください。
河野 : ひと通りやった経験をもとに、今年度に向けての段取りをしているところで、藤吉先生にいろいろ相談しているところです。最近、生成AI関連の情報が激しくアップデートされていますね。そのあたりは各メンバーも敏感ですので、トークルームで、お互い手を動かしながら情報をアップデートしています。そもそも弊社は技術の交流やコミュニケーションが活発で、風通しのいい組織だと思っています。みんな和気あいあいと情報交換していますね。
南野 : 社内での技術発表を定期的にやっています。社内で技術を学ぶサークルがあって、そういうものに参加しているメンバーもいますし、技術をみんなで共有する文化が、強く根付いている会社だと思います。
河野 : まずはE資格を勉強して取得した人をしっかり評価していきます。E資格取得についての情報は、営業用資料にも反映させるべくブラッシュアップしているところです。
――ありがとうございました。