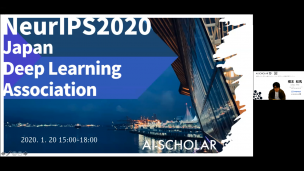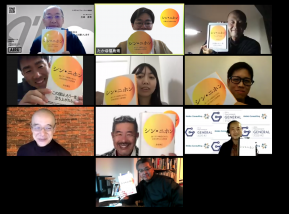【3/18 製造現場へのAI・IoT普及セミナー& ものづくりIoT研究会 第5回定例会】
名 称: 「製造現場へのAI・IoT普及セミナー&ものづくりIoT研究会第5回定例会」
主 催: 公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ、滋賀県
しが新産業創造ネットワーク「ものづくりIoT研究会」
滋賀県工業技術総合センター「現場力の維持・強化に向けたAI開発支援事業」
会 場: コラボしが21 3階 大会議室 (滋賀県大津市打出浜2-1 )
日 時: 2021年3月18日(木)14:00~17:00
参加費:無料
定 員:70人(先着順)※申込期限は3/11(木)
登 壇:
「中小企業はAI をこう使おう!」
講師:岡田 隆太朗 氏
[一般社団法人日本ディープラーニング協会 理事・事務局長]「生産現場に価値を生むAIシステム」
講師:藤田 圭佑 氏
[Musashi AI株式会社 AIエンジニア(日本ディープラーニング正会員社)]詳 細:https://www.shigaplaza.or.jp/semina-mono-210318/
【3/9 FOODEX JAPAN 2021 川上理事 セミナー登壇】
名称: FOODEX JAPAN - フーデックス ジャパン2021(第46回 国際食品・飲料展)
主催:一般社団法人日本能率協会
一般社団法人日本ホテル協会
一般社団法人日本旅館協会
一般社団法人国際観光日本レストラン協会
公益社団法人国際観光施設協会
会場: 幕張メッセ(千葉市美浜区中瀬2-1)
日時:3月9日(火)15:00-16:00
入場・登録料: ¥5,000(税込)「招待券」持参者は無料。
※講演は 、聴講無料・ 事前登録制 です。
登壇:
「 技術の進歩とディープラーニング活用による食品業界の未来」
川上 登福 (一般社団法人日本ディープラーニング協会株式会社経営共創基盤・共同経営者マネージングディレクター)
講演概要: 食品業界においても様々な場面において導入が進むディープラーニング技術について、実際の導入事例と課題を含めた最新トレンドが解説される。
詳細:https://www.jma.or.jp/foodex/seminar/foodex.html#seminar_kawakami
【JDLA主催 NeurIPS 2020 技術報告会 1/20開催】
1月20日(水)15:00より、2021年最初のJDLA主催イベントとなる「NeurIPS 2020技術報告会」が開催されました。
「技術報告会」とは、国内外で開催される、ディープラーニングに関する学会やイベントの最新情報を日本ディープラーニング協会の会員およびCDLEメンバー向けにご紹介するためのイベントです。対象は、国際学会・国内学会・さらに日本ディープラーニング協会の会員企業が海外で行うディープラーニングが主なテーマの商業イベントなどです。これまで、2020年4月17日にNVIDIAのGTC 2020報告会、2020年7月15日にCVPR 2020技術報告会が行われています。
今回は、機械学習分野の世界最高水準の学会であるNeurIPS(Neural Information Processing Systems) 2020の報告会でした。
NeurIPSは1987年に始まった歴史のある学会で、AlexNetやTransformerなどAIの歴史を変えるような、様々な革新的な発表が数多くされた学会として有名です。またNeurIPSは、発表される論文数の多さでも知られています。2020年は9,500件ほどの投稿に対し、約2,000件の論文が採択されています。
これを一人で読むのは事実上不可能ですが、今回の技術報告会では、JDLAのメディアパートナーであるAI-SCHOLAR様のご協力の元、JDLA会員およびCDLEメンバーが聴講者であることを想定して、論文を選んで頂きました。
そして、今回の技術報告会では、5人の方から計9本の論文について、それぞれ研究の背景や提案手法の紹介、その実験結果などが紹介していただきました。
NeurIPS 2020報告榎本和馬One-bit Supervision for Image Classification
Neuron Shapley: Discovering the Responsible Neurons中島佑允Sampling from a k-DPP without looking at all items
Baxter permutation process中野允裕The Lottery Ticket Hypothesis for Pre-trained BERT Networks
Pruning neural networks without any data by iteratively conserving synaptic flow
All Word Embeddings from One Embedding高瀬翔Delay and Cooperation in Nonstochastic Linear Bandits伊藤伸志Deep Energy-Based Modeling of Discrete-Time Physics谷口隆晴
世界最高のAI学会での最新発表の論文ですので、その内容を理解するというのは多くのCDLEメンバーにとっても難しかったとは思いますが、世界の最先端ではこんなことが起こっている、という雰囲気は感じ取って頂けたのではないかと思います。
JDLAでは、今後もこのような世界最先端の技術報告会を続けていきたいと思っています。
レポート: 日本ディープラーニング協会事務局 CDLE担当 林 憲一(G2018#2, E2019#1)
【1/18~31 岡田隆太朗事務局長登壇】The AI Powered by HP 特別講演
主催: 株式会社日本HP / 株式会社レッジ
会場: オンライン(特設サイト内)
日時: 2021年1月18日(月)~31日(日)
※ 2021年2月1日(月)~ サイトアーカイブ予定
登壇: Special Lecture 特別講演
『AIスペシャリストたちの視座から探る、2021年求められる人材とスキル』
- 株式会社レッジ 代表取締役 橋本 和樹
- 日本ディープラーニング協会 理事 事務局長 岡田 隆太朗
- 株式会社ABEJA 執行役員 菊池 佑太
新型コロナウイルスの世界的な流行によって、様々な生活様式が一変し、私たちのビジネスを取り巻く環境についても劇的に変化しました。そんな状況下で私たちは、「ニューノーマル時代」においてどのようなスキルを身につけ、どのようなキャリアを歩んでいけばよいのでしょうか?AI業界の有識者と議論していきます。
詳細:https://the-ai.jp/
【CDLEイベントレポート】第1期『シン・ニホン読書会』
11月4日を皮切りに12月16日まで毎週1回の全7回シリーズとして、第1期『シン・ニホン読書会』が開催されました。
今回は、その第1期『シン・ニホン読書会』についてのレポートです。
◆概要
日程:全7回(11/4、11、18、25、12/2、9、16、21の21時から、各回約1時間)
◆『シン・ニホン読書会』の趣旨
<シン・二ホン読書会アンバサダーは、「未来を目指し、創るものだ」に共感したものが集う人たちのコミュニティである。 「シン・ニホン」を読む人が増えれば、未来のために自ら動こうとする人が増えるはずである。未来のために動こうとする人が増えれば、この国の希望の総量は増すはずである。>
また副題として、「AI×データ時代における日本の再生と人材育成」を掲げており、CDLEから「未来を目指し、創る」AI人材を増やしていくことを目指します。
◆レポート
初めての読書会企画となる『シン・ニホン読書会』では、「輪読」や「内容の共有」ではなく、「シン・ニホン」の内容を踏まえ、毎回議論のための「問い」を設定し、参加者同士、「問い」を基に議論を行いました。
参加者は、20代から60代までの多世代の方々で構成され、世代間の交流も持つことができました。若い人は今までの歴史の振り返りを、年配者は若い人の考え方の理解など、それぞれ得るものが多く、参加者にとって大きな刺激になりました。 職種も、エンジニア・営業・コンサルタント・会社経営者など、様々な立場の方々が参加されました。
「シン・ニホン」という良書を共通話題として交流することで、日常から離れた関係のなかで議論を交わすことができました。さらに、非日常的な関係性を保ち本の内容からいったん離れることで、参加者の発言する意見から新たな触発を受け、一人では生み出せない考え方の化学反応のような新しい考え方が産まれることもありました。
このような体験を通して、未来に対し「自分事として活動を行いたい」と思われる方も複数おられました。この『シン・ニホン読書会』の趣旨と副題「AI×データ時代の中核となるAI人材を、CDLE内で増やしていくこと」を目指している本読書会でしたが、開催のための趣旨が伝わったのではないかと感じることができました。
◆読書会全体に関するアンケート(自由記述)回答
「読書会は楽しかったです。仕事柄、初めての方にお会いして刺激を与えあうということは珍しくはないですが、ある意味志を同じくした同士との語らい合いはまた格別でした。シリコンバレーで言われていたような、イノベーションに向けてのソサエティが日本ではWeb上で出来上がっていくといいなと思います。」
「この度は読書会を開催してくださりありがとうございました。本の内容を掘り下げるだけではなく、参加者各々が意見や知見を語り合う会であったことがとても勉強になりました。自分が所属しているコミュニティ(会社・居住地など)では出会うことができなかった方々と一緒に参加できたことも良かったです。是非もっとたくさんの方々にシン・ニホンを読んでいただきたいなと思います。また、今後は実際に自分自身が日本を良くするために何ができるかを考えて行動に移していきたいと思います。今後とも宜しくお願いいたします。」
「同じ問題意識の方と意見交換ができるという非常に良い機会ももてた。」
「自由度が高く、ストレスなく参加できた。話すより聞くことを心がけたので、いろんな話が聞けた。本を一冊読み切るのは大変なパワーが必要だが、読書会がマイルストーンになって、最後まで読み切れた。以上が、よかったと感じた点です。ありがとうございました。」
「全国各地で年齢も様々な方たちとG検定&シン・ニホンという共通点で話し合えたことは楽しかったです。」
「まず、非常に優秀かつ似たようなビジョンをもつ方々が集まっている印象でした。CDLEというプラットフォームを介している故かと思いますが、この場自体が非常に貴重だと思います。全7回を通して得たものは、きっちり書籍を理解することと、自分に置き換えたときどう想像するかを訓練できたことかと思います。ファシリテートも毎回丁寧に設計いただきありがとう
【1/27 江間有沙理事登壇】
JMA GARAGE2021「 The Future of Japan 」
主催: 一般社団法人日本能率協会(Japan Management Association)
会場: オンライン開催
日時: 江間理事登壇 1月27日(水)13:00~14:30
受講料:有料
登壇:江間有沙理事「 AI社会の歩き方 」
▼詳細はこちら
https://jma-innovation.com/
江間 有沙東京大学 特任講師/
日本ディープラーニング協会 理事
AI社会の歩き方
AIやデータに関する課題の事例AIガバナンスの国内外の動向多様なステークホルダーの議論から生まれる価値 講演概要AIをめぐっては安全性、公平性、説明可能性など様々な課題があります。本講演では国内外における様々な事件や事例を紹介しながら、AIやデータ利活用に関するルールや枠組み作りの実践を紹介します。各研究者や企業のみで取り組めるガバナンスもある一方で、AIの「学習する」という特性や、データを共有するという目的によっては、組織の枠を超えたガバナンスの在り方を模索する必要性も出てきます。競争領域でありながらも競争域であるAIとデータをめぐる課題について、多様なステークホルダー間の議論を介して、私たちの今後の望ましい社会の在り方や作り方について考えていきます。
PROFILE東京大学未来ビジョン研究センター特任講師。2017年1月より国立研究開発法人理化学研究所革新知能統合研究センター客員研究員。専門は科学技術社会論(STS)。人工知能と社会の関係について考えるAIR(Acceptable Intelligence with Responsibility)研究会を有志とともに2014年より開始。人工知能学会倫理委員会委員。日本ディープラーニング協会理事兼公共政策委員会委員長。2012年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。
聴きどころAIを用いたデータの利活用について戦略を練る際、欧州のGDPRに代表されるように、国内外における様々な規制や事例を鑑みることが求められます。企業単体で取り組めるガバナンスとは何か?また組織の枠を超えなければ取り組めないものはなにか?本セッションでは東京大学の江間氏にご登壇いただき、競争領域でありながらも競争域であるAIとデータをめぐる課題について、私たちの今後の望ましい社会の在り方や作り方について考えていきます。
CDLE関西主催『ディープラーニングを語ろう会 - The Grand Aim - 』イベント報告(2020.12.7開催)
12月7日(月)に、CDLE関西が主催する「ディープラーニングを語ろう会 - The Grand Aim - 」が開催されました。
「The Grand Aim」とは、AIをビジネスや生活に活かそうとしている人たちの"夢"や"思い"が重なり大きくなっている様子を表した造語です。
イベントには機械学習やディープラーニングに興味を持った37人が集まり、「The Grand Aim」に則って人工知能技術で実現できる自分の夢や一歩先の未来について語り合う会となりました。
いつもの定番であるLTは、DLT(ドリームLT)と名前を変えて自分自身の目標や思いを発表してくださいました。
DLTタイトルは以下の通り。
◆自然言語処理を活かした未来のコミュニケーション
◆他流試合で最強のEvangelistに成長しよう
◆この一年の振り返りと未来に向けて
DLTが終わった後は参加者全員の夢を共有する時間として、Remoを使った交流会を行いました。
参加者たちは自然とテーブルに集まって秩序良く楽しく夢を語りあいました。
参加者の夢の中には以下のような夢がありました。
・自然言語処理を活かして、言葉の壁がない世界を実現したい
・素材を元にデザインをAIで生成できるようになりたい
・AIを使って新しい社会を切り開いていく一助になりたい
・世の先例となるような、独自の機械学習の手法を生み出す
・自由にDLが使えるようになりたい
・会社の次世代の柱となるソリューションを自部門で開発したい
・データ分析によって人のことをより理解し、人の生活を助けてより人が楽しく健康に生活できるようなサービスを作りたい
・生きているようなキャラクターと交流するサービスを作りたい
・自分が開発したシステムにAIを組み込む
・ヒューマンデータサイエンティストになる
・誰もが認める世界トップの企業にしたい
・社内でAI/DLのナレッジシェアをしていきたい
・ソフトウェア関連の会社とハードウェア関連の会社の橋渡しとなるようなこともしていきたい
・まだ世の中にない新しいものを作りたい
・残りの人生を完成させる
・くだらないことでもいいので、まだ誰もやったことがないことをしたい
・人それぞれの個性が活かされて、個人を尊重され、貧困や戦争がない星になって欲しい。そうしていきたい。
・将来的にAIに関係する自分の好きな仕事をする
・CDLE関西のメンバーで社会貢献したい
参加者全員がこの時間に語り合った"夢"は、すでに皆の「The Grand Aim」となりました。
今後、夢が叶えられた時の喜びも皆で共有できればと思います。
さて、CDLE関西でも新たなる大きな目標を掲げました。
それは2025年に開催される「大阪・関西万博」を、なんらかの形でCDLE関西が関わって成功させるということです。
簡単なことではないと思いますし、課題もたくさんありますが、参加者の皆さんからの熱いエール、貴重なアドバイスも頂きました。
CDLE関西はこの決意をもって、参加者全員と共有した「The Grand Aim」を掲げ、今後もCDLE関西として前へ前へと前進してまいります。
レポート協力: CDLE関西 趙 成哲さん
~ご協力をありがとうございました~
CDLE DAY 2020 開催レポート (2020.11.28開催)
JDLAの資格試験合格者のみが参加できるコミュニティ「CDLE」の大規模イベントが11月28日に開催されました。
CDLEは3万人を超える日本最大規模のAIコミュニティとなっていますが、今回のようにCDLEそのものにスポットを当てたイベントは初めてです。
今までの活動や今後の企画等が次々に発表され、コミュニティメンバにとって新たな気付きが多く得られる時間となりました。
休日にも関わらず、参加申込者は約1300名、YouTube Live視聴者は約1000人となりました。
<イベント概要>
・名 称 CDLE DAY 2020
・開催日時 2020年11月28日(土)10時00分-13時00分
・内容 1.JDLAアップデート(日本ディープラーニング協会 理事 事務局長 岡田 隆太朗)
2.特別講義 (東京大学 未来ビジョン研究センター 特任講師 江間 有沙)
3.CDLE VIEW(CDLEコアメンバ)
1.JDLAアップデート
イベントは、日本ディープラーニング協会の事務局長 岡田氏より、協会の活動紹介からスタート。
今回のイベント形式がYouTube Liveで配信され「見返し」が可能であることに触れながら、オンラインであることの利点も生かして会に参加してほしい、というメッセージがありました。また、他資格との連携など合格者には嬉しい情報も発表されました。
CDLEとの関係性については「協会はCDLEを『依怙贔屓』します」とコミュニティ活動に対する全面的なバックアップ宣言が飛び出しました。
2.特別講義「G検定教科書 9章に苦しめられてきた人たちへ」
第二部は、東京大学 未来ビジョン研究センター 特任講師 江間 有沙 先生からの特別講義です。G検定を受験された方の多くは、講義タイトルに「私のこと!?」と感じたのではないでしょうか?
G検定の第9章は「法律・倫理・現行の議論」「AIと社会」といった、多くの受験生を悩ませてきたと言われる問題が多く含まれています。その9章の執筆者の1人である江間先生から、この章が何のために存在するのかについて、AIと社会の関係性の具体事例を上げながらお話いただきました。
今の社会に必要なものは何か、その答えは刻一刻と変化します。何が重要かを見極めるためには様々な視点が必要であることから、自分のまわりに「たりない」視点が何かを立ち止まって考えてみることも大事です、という助言がありました。
ブラジルのAI社会実装例などの事例をもとに、ディープラーニングの社会実装にあたり、倫理的な問題や社会課題に対してどう向き合うべきかについて、コミュニティメンバに深く問いかける講義でした。
3.CDLE VIEW
第三部は、今回のイベントタイトルでもあるCDLE自体の紹介を行う時間となりました。
ここで、進行役は総合司会のJDLA(CDLE担当)の林さんから、CDLEコアメンバの為安さんにバトンタッチ。
以降のパートは、CDLEコアメンバが交代しながらリレー形式での進行となりました。タイトルは「CDLE VIEW」。コミュニティの展望や未来、という意味が込められているそうです。
為安さんからは、CDLEの定義や大事にしたい考え方がはっきりとした形で提示されました。
また、これまで曖昧だったCDLEとJDLAの関係性については図式で説明され、「CDLEはJDLA内の組織ではなく、互いに支え合う関係にあります」という説明に驚い
【12/21 岡田事務局長登壇】
東京都中小企業振興公社webセミナー「中小企業でもAIは使える!」
主催: 公益財団法人東京都中小企業振興公社
会場: Web会議室ツール「Zoom」
日時: 2020年12月21日(月)14:00~16:00(視聴可能開始時刻13:50)
受講料:無料(先着100名様)
※ 申込〆切は、2020年12月17日(木)12:00
※ 都内に主たる事業所がある中小企業 が対象となります。
登壇:JDLA岡田事務局長
14:05-14:55 「第1部 中小企業はAIをこう使おう!」
▼詳細はこちら
https://iot-robot.jp/seminar/iot-seminar-20201221/?fbclid=IwAR26Bwwyh_I1qObEo4z6uj_eZr0jVl5D7TxbaV8uKisZPWnc-eO_9aSOJIM
中小企業でもAIは使える!~2020年度 第4回 普及啓発セミナー(AI)~
近年、人手不足の深刻化や生産性向上への期待から、中小企業においてもAIの活用に対する関心が一層高まっています。
本セミナーでは、「中小企業がAIを導入するには」「ビジネスへのAI導入事例」「中小企業がAI導入を進めるためのプロセス」「成果を上げられる分野と導入事例」といったテーマで、中小企業のAI導入に関して、具体的なイメージをお持ち頂けるようお伝えいたします。
是非ともご参加ください。
【12/19 松尾理事長 登壇/後援】 高専キャラバン2020 冬の陣
主催:フラー株式会社
協力: 広島県 / ひろしまサンドボックス、ZENPEN、株式会社高専キャリア教育研究所、
株式会社TechBowl、株式会社プロッセル、高専マガジン、株式会社エニバ
後援: 独立行政法人国立高等専門学校機構、一般社団法人日本ディープラーニング協会DCON実行委員会、
Empowered JAPAN実行委員会
会場:オンライン開催
日時:12/19(土)、12/23(水)
参加費:無料(要事前申込)
登壇:
◆基調講演①:12/19(金)17:55-18:10
「ディープラーニングと高専の可能性(仮)」
・松尾豊 東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究センター/技術経営戦略学専攻 教授
◆パネルディスカッション①:12/19(金)18:25-18:55
「これからの時代に求められる高専とその可能性(仮)」
・ 松尾 豊 氏
東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究センター/技術経営戦略学専攻 教授
・ 湯﨑 英彦 氏 広島県知事
・ 渋谷 修太 氏 フラー株式会社 代表取締役会長
・ 川野 晃太(ファシリテーター) フラー株式会社
詳細:https://kosen-caravan.com/
【12/11 松尾理事長登壇】
SEMICON Japan Virtual
パネルディスカッション「AIが切り開く未来と技術チャレンジ」
主催:SEMI
会場:オンライン開催
日時:2020年12月11日~18日
◆松尾理事長 講演 12月11日(金)15:30~◆
パネルディスカッション「AIが切り開く未来と技術チャレンジ」
参加費:有料
詳細:
https://www.semiconjapan.org/jp/programs/conference/keynotes/session-2
(引用)
映画「スターウォーズ」が描いたロボットによる通訳や宇宙船操縦のシーンが、現実となりつつあります。AIシステムとの会話は、もはや日常的な光景といえるでしょう。 人工知能(AI)は、今世紀にはいり深層学習やビッグデータが登場すると急速に社会に浸透し、私たちの暮らしや仕事にも様々な変化をおこしています。
本セッションでは、日本を代表するAIの研究者である東京大学 松尾豊教授、黒田忠広教授の対談を通じて、AIによって切り開かれる未来の可能性と、そのハードウェア基盤となる半導体技術の最先端について明らかにしていきます。モデレーターには、ニュースキャスターの小谷真生子氏があたります。
【11/27 松尾理事長登壇】
ISID X(クロス) Innovation フォーラム 2020
<デジタルを日常へ、リアルを革新へ ~ 一新された世界で ~>
主催: 株式会社電通国際情報サービス
会場: LIVE配信
日時: 2020年 11月25日(⽔)〜12月15日(火)
◆松尾理事長講演 11月27日 10:00~◆
受講料: 無料(事前登録制)
登壇: 松尾豊
(東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究センター
技術経営戦略学専攻 教授、
一般社団法人日本ディープラーニング協会 理事長 )
<ディープラーニング技術の大きな可能性とそれを支える人材の育成>
本講演では、人工知能の最新動向、特にディープラーニングを取り巻く状況について述べる。ディープラーニングの仕組みや人工知能における意義を解説し、さらに今後、どのように人工知能の技術が発展するか、また、人工知能の発展が産業や社会、それを支える人材の育成に与える影響やその可能性について解説する。