委員長 八木聡之(富士ソフト株式会社 常務執行役員)
設立趣旨
近年の生成AIの急速な発展に伴い普及が急速に進むAIの利活用にあたっては、個人情報保護法や著作権法などの様々な法令に留意する必要がありますが、これらの法令が制定された当時には想定されていなかったような態様でのデータの取得や利用が可能になっており、法解釈が明確でないものも少なくありません。企業としては、このような未知の問題に対し、ステークホルダーの権利・利益を尊重しつつ、リスクを適切に判断し、合理的な範囲でリスクテイクする判断をする必要があります。リスクを過小評価すると法令違反やレピュテーションの毀損が生じえますが、リスクを過大評価するとイノベーションの障害となり、海外企業に先行を許すことにもなります。
本委員会は、AIに関する法律・技術・ビジネスの専門性を有する委員が議論して議論内容を公表すること、及び議論内容を踏まえて積極的にAI利活用の前例を作出することを目的として立ち上げられました。
本委員会では、既に専門家の間で一定の法解釈が一般的になりつつある事項から、法解釈や実務が十分に固まっていない事項まで、AIの利活用にとって重要な影響を与える様々な問題を議論しています。このような事項について、委員が専門的な知見を踏まえ、法・技術・ビジネスの実態を架橋して議論することで、正しくリスク評価を行うとともに、議論内容を公表することで今後の議論の発展や問題提起につながります。また、あるべきルールを提案し、当該ルールの利用者を増やしていくことで、商慣習や契約内容などを標準化し、AIの利活用を適切かつ迅速に進めることができるようになります。さらに、法的な「論点」とされているものの中には、技術・ビジネスの実態と整合していない、または時代遅れになっているものもあり、この点を問題提起することにも意義があります。
以上のような委員会における議論に加え、議論を踏まえてAI利活用の前例を作出することにも取り組みます。前例があるという事実は、企業の意思決定にあたって非常に大きな意味を持つことはいうまでもありませんが、一般化すれば法的な意味での「慣習」にもなり得ます。慣習は、法令に規定されていない事項に関するものについては法律と同一の効力を有しうるほか(法の適用に関する通則法3条)、法令に優先する場合もあります(民法92条)。また、慣習は、司法の場で法解釈にも重要な影響を与えるほか、立法の際には立法事実として考慮され得ます。
日本は、企業が法的リスクに対して保守的な対応をとる傾向にあり、また、訴訟が起こりにくく、司法によるルール形成プロセスが他国と比べて十分とはいえないなどの要因から、AIなどの新しい分野に積極的に取り組むことが容易ではありません。そのような状況において、本委員会の取り組みは、AIの開発・ビジネスにおける新しい標準を作る活動として非常に重要な意義を持つと考えております。
本委員会の活動に、多くの企業の方々、技術者や研究者の方々及び専門家の方々がご賛同及びご参加いただければありがたいと思っております。
成果物
『法と技術の検討委員会報告書ー AI 開発に関するユースケースー』
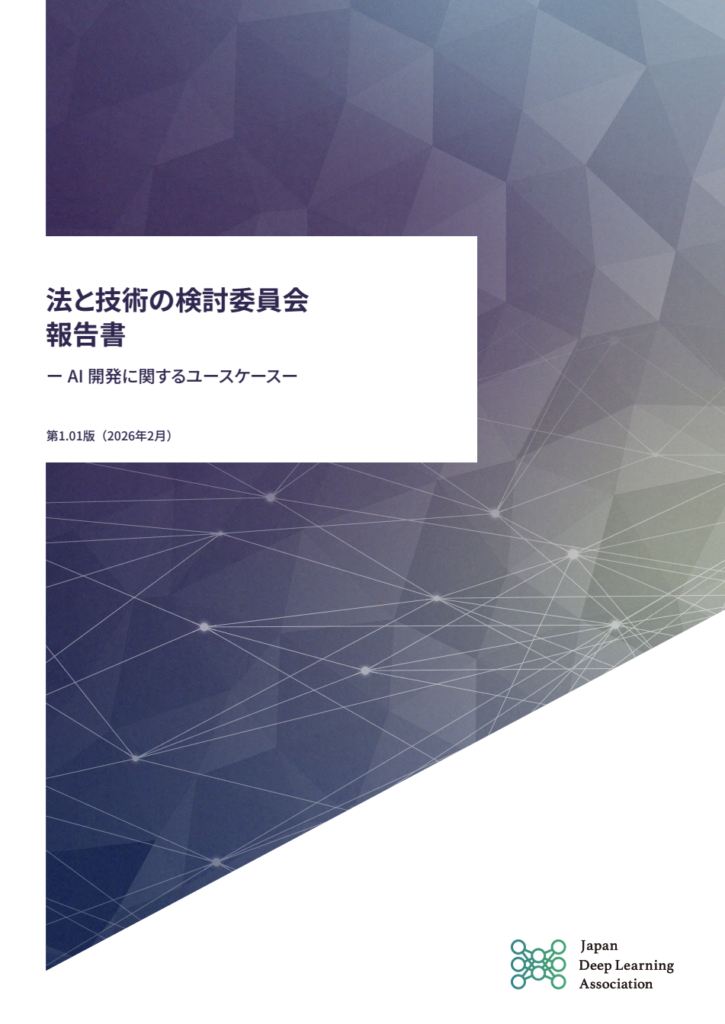
『法と技術の検討委員会報告書Ⅱー AI 利用に関するユースケースー』
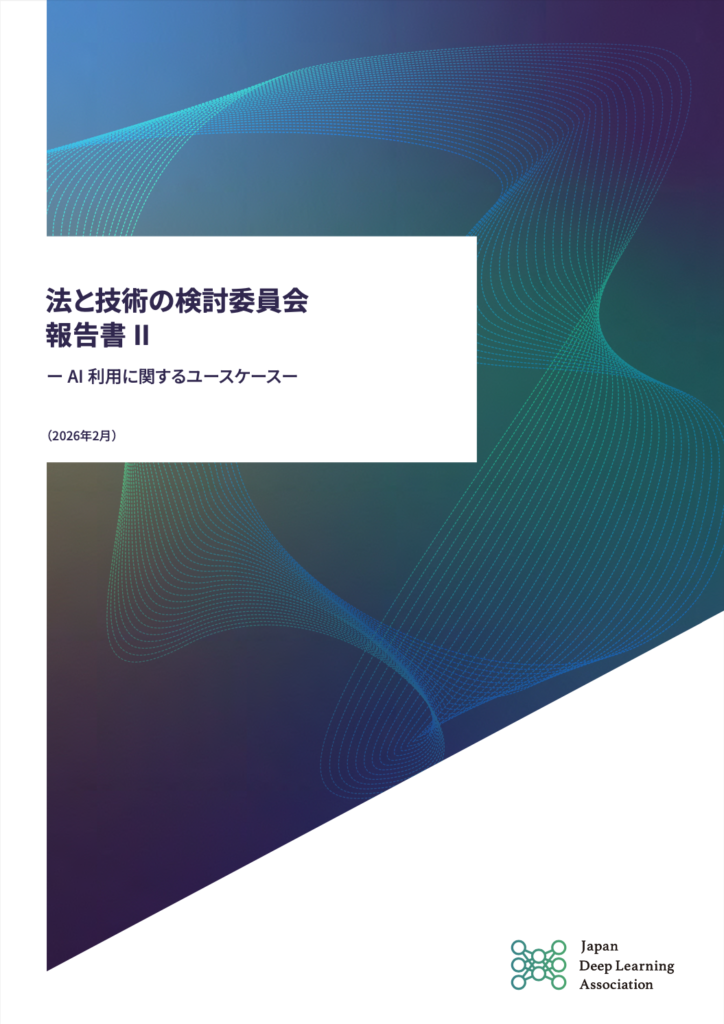
委員会の議論に基づく前例
「法と技術の検討委員会報告書ー AI 開発に関するユースケースー」(2025年3月)に記載された見解に基づき、以下のような前例が作出されています。
報告書・Case1: 委託を受けた個人データを利用したAIの開発
- AIの開発を受託したベンダ企業が、委託したユーザ企業から開示を受けた介護に関する個人データを用いてAIを開発し、開発したAIは、ベンダ企業とユーザ企業の契約に基づき、横展開をすることを前提に開発を進めている事例
- 作業員の姿勢を推定するAIの開発を受託したベンダ記号が、委託したユーザ企業から開示を受けた、作業中の従業員を撮影した画像データを用いてAIを開発し、開発したAIは、ベンダ企業とユーザ企業の契約に基づき、横展開をすることを前提に開発を進めている事例
報告書・Case2: 第三者の著作物を含むデータセットの提供及びCase3: 要配慮個人情報が含まれるデータ収集
- 東京大学の松尾・岩澤研究室より、クローリングにより収集したテキストデータに含まれる要配慮個人情報をフィルタリングするフィルタリングモデル(以下「本件フィルタリングモデル」といいます)が公開されています。こちらよりご確認ください。
- また、同研究室は、本件フィルタリングモデルを用いて要配慮個人情報をフィルタリングしたデータセットを公開しています。こちらよりご確認ください。
- 株式会社ABEJAは、既に同社において要配慮個人情報をできる限り減少させる等の措置を講じたうえで公開したデータセット「ABEJA CC-JA」を公開していますが、さらに本件フィルタリングモデルを用いて要配慮個人情報をフィルタリングしたデータセットを公開しています。こちらにて公開されているS3バケットの”ppi_filterd/”配下に存在しますので、ご確認ください。
報告書Ⅱ・Case1:生成AIへの個人データの入力
- ChatGPT、Gemini及びMicrosoft 365 Copilotについて、一定の条件下で個人データの入力を行っている事例を複数確認しています。
報告書Ⅱ・Case2:AI生成物の著作権
- 一定の条件下で本報告書の方針と同様の運用を行っている事例がございます。
※ 本委員会及び前例やフィルタリングモデル等を公表した組織は、公開した内容の適法性等を保証するものではありません。
相談窓口
AI活用に際して企業が直面する法的課題は、専門的な知見を必要とするものや、現行法では対応が難しいものも多いため、法・技術・ビジネスの各分野の専門家による連携が不可欠です。JDLAでは、このような法的課題を収集・集約し、必要に応じて本委員会と連携して対応するため、相談窓口を設置いたしました。窓口からご相談いただいた企業が直面する法的課題を一元的に集約し、1社では対応が難しい課題について、本委員会と連携し、適切な対応を進めてまいります。
なお、本相談窓口は、個別のご相談に対する回答を目的としたものではなく、弊協会においてAIの活用に関する問題点を集約し、必要に応じて検討をさせていただくものです。いただいたご相談についてのご返信をお約束するものではございませんので、ご了承ください。
